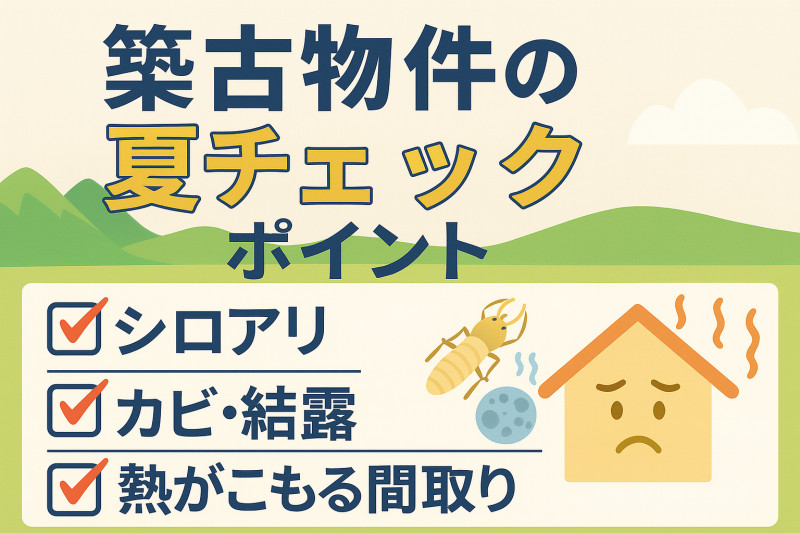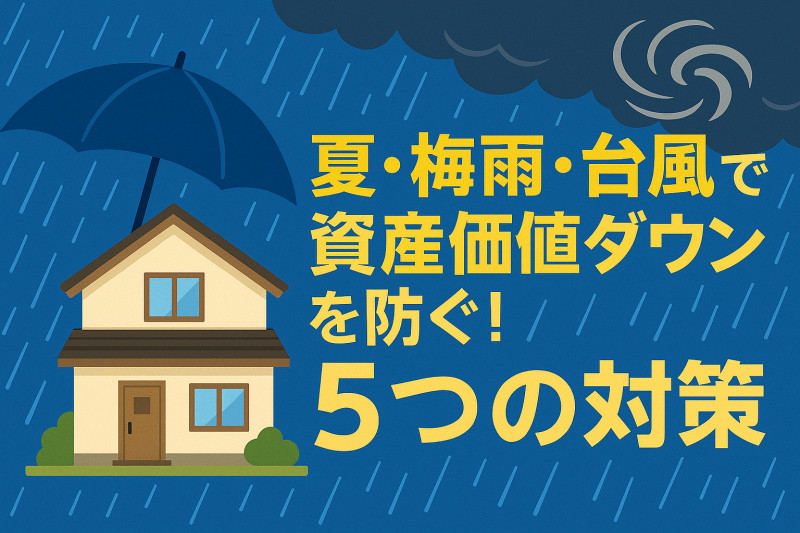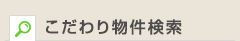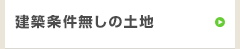既存住宅瑕疵保険について。
既存住宅(中古物件)瑕疵(かし)保険について
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)って聞いたことありますか?
不動産売買契約書の条文の中にも謳れているのですが、
売買契約の目的物(購入したもの購入した時点では明らかになっていない、隠れた瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことです。
民法において、
新築のマイホームを購入した際に購入者の保護を目的にした「住宅瑕疵担保履行法」というものがあります。
建築業者は瑕疵が発覚した際の対応用の資金確保のための保険に加入することを義務とされ、仕組みが出来あがっています。
中古物件の購入やリフォームについては、任意の「瑕疵保険」に入ることで建物に欠陥などがあった場合に補修費用が支払われる仕組みがあります。
今回は、このあまり聞かない言葉、瑕疵保険についてご説明します。
中古物件の売買では、売り主が個人の場合の瑕疵担保責任は長くて3か月程度(都城市の場合は現状有姿が多いですが…)、売り主が宅建業者の場合で2年間です。
この期間を過ぎてから住宅に瑕疵が見つかった場合は、その補修は買い主が行うことになります。
それを回避するために、「既存住宅売買瑕疵保険」があります。この保険は引き渡しを受けた住宅に瑕疵があった場合に補修費用をカバーしてくれるものです。
既存住宅売買瑕疵保険には、「個人間売買タイプ」と「宅建業者販売タイプ」の2種類があります。
個人間売買タイプは、保証を行う検査機関が加入する保険で、宅建業者売買タイプは宅建業者が加入する保険です。
中古物件は売り主が個人のケースが多いです。
個人の場合には、まず売り主が検査機関に対して「検査」と「保証」を依頼します。
依頼を受けた検査機関は、対象の住宅を検査して、瑕疵保険に加入します。
それと同時に、買い主に対して検査機関が保証します。
もちろん、買い主が検査機関に検査と保証を依頼するのもOKです。
既存住宅売買瑕疵保険の保険期間は、住宅の引き渡しから5年間なので、3か月から大幅に延びます。
対象になるのは、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分などです。
保険の上限は1,000万円で、補修費用、調査費用、補修工事中の転居・仮住まい費用なども保険支払いの対象になります。
注意点は、対象の住宅が新耐震基準に適合しているなどの一定の条件をクリアする必要があること、保険加入時に保険料と現場検査手数料が必要になること、などです。
リフォームについては、「リフォーム瑕疵保険」があります。
これはリフォーム工事に欠陥などがあった場合に、補修費用などが事業者に支払われ、リフォームを依頼した側は無料で修繕してもらえる保険です。
保険に加入するのはリフォーム業者で、あらかじめ保険法人へ事業者登録をしておかないと保険に加入できません。
リフォーム瑕疵保険の契約では、リフォーム工事の施工中や工事完了後など、工事の内容によって第三者検査員による検査が行われます。
検査を行うことで、ずさんな工事や過剰工事などの工事に関するトラブルを未然に防ぎます。
リフォーム瑕疵保険は、概ね最大1,000万円が保険の対象で、補修工事中の仮住まい費用なども対象になります。
保険期間は、5年または1年で、工事内容によって異なります。
保険の詳細は保険法人によって異なりますので、確認が必要です。
ちょっと内容が難しいですね。ご不明点などあればお問い合わせください。
宮崎県都城市前田町7街区22号 拓新ビル2階
0986-36-6066 / 0986-36-6882
営業時間:9:00~19:00
定休日: 年中無休(年末年始・お盆は要予約)