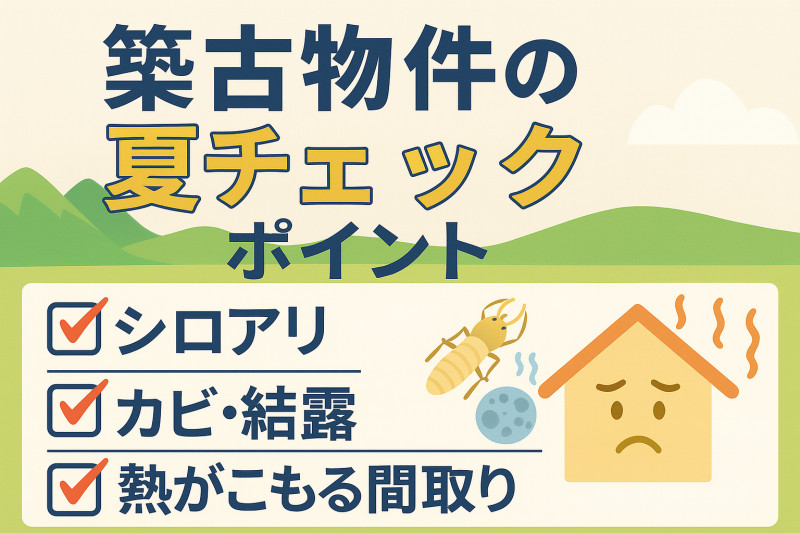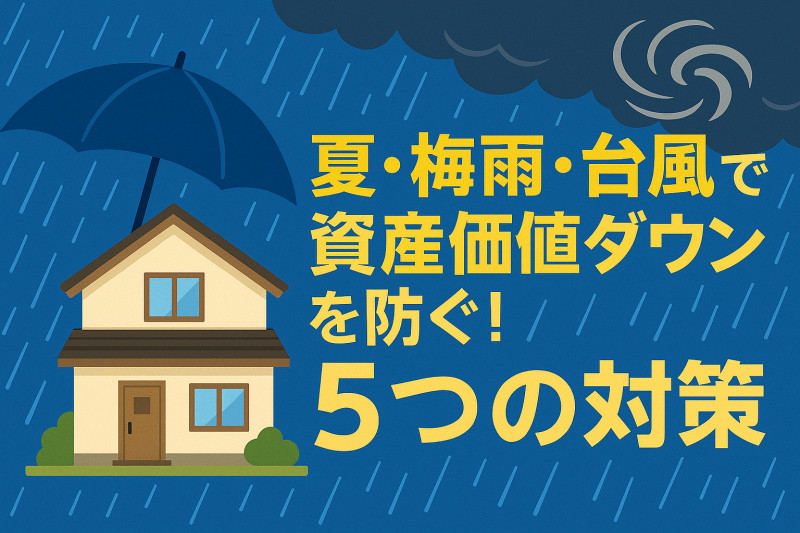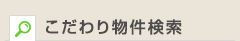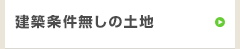土地の価格の決め方。一物五価とは?
毎年9月に、宮崎県が7月1日時点で「基準地価」というものを発表します。
それが昨日発表されました。
報道されていたのでご存じかもしれませんが、この価格は景気の目安としても使われますし、マイホームの購入価格にもつながってくる価格です。
ちなみに、宮崎県で一番高い土地と評価を受けたのが、宮崎市橘通東3丁目の旭屋で34年連続トップだそうです。
こんな土地、持ってみたいですね。
話がそれました。土地の価格の話に戻りましょう。
不動産は「一物五価」と言われています。
どういう意味かというと、不動産の価値を示す基準には5つの数値がある、ということです。
具体的には、以下5項目になります。
①実勢価格(売買取引価格)
実際に行われる不動産の取引で、需要と供給のバランスが釣り合う価格を実勢価格と言います。言ってみれば不動産の時価です。
実勢価格は、最近の取引事例や、近隣地域の取引を参考にして出されます。
②地価公示
国道交通省が発表する土地価格の基準です。一般の土地取引の指標のためと、公共事業の適正な補償金の算出を行うため、などに使用されます。毎年1月1日を基準にして3月の公表されるもので、土地取引に最も影響する指標とされています。
③都道府県地価調査(基準地価)
都道府県が全国から2万数千件の基準値を選び、毎年7月1日を基準にして9月に公表する地価です。地価公示の半年後に公表されるため、その間の地価の変動を反映して、地価公示を補完するための役割を持ちます。
④相続税路線価
国税庁が相続税や贈与税の算定に基準とするために公表する数値です。宅地が面する道路に設定された標準的な価格を基準に評価します。
毎年1月1日を基準に、7月初旬に公表します。相続税路線価は地価公示の約8割の評価額となっています。
⑤固定資産税評価額
各市町村が固定資産税などの課税のために出す評価額です。3年ごとの基準年度の前年1月1日を基準に、3月か4月に公表されます。公示価格の約7割となっています。固定資産税評価額は固定資産税以外にも、登録免許税や不動産取得税の課税の基準にも使われます。
以上の5つが不動産の価格を決める「元」になる数値です。
それぞれ目的が異なっていますので、用途によって使い分けも必要となります。
不動産会社が行っている不動産価格の査定は、基本的に①の実勢価格(売買取引価格)を基準にして、おおむね3か月で売却できるであろうという金額を出します。
そういう感じで土地の価格は決められているのです。
宮崎県都城市前田町7街区22号 拓新ビル2階
0986-36-6066 / 0986-36-6882
営業時間:9:00~19:00
定休日: 年中無休(年末年始・お盆は要予約)